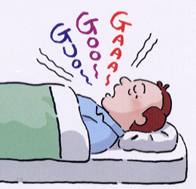
今回は糖尿病や高血圧を引き起こす原因は、
睡眠時間無呼吸症候群が原因になることに
ついてご説明したいと思います。
睡眠時間無呼吸症候群は血管が傷ついたり、
インスリンが働かなくなることも!
睡眠時間無呼吸症候群とは、眠りが浅くなり、日中の居眠り運動などの
原因になるとされています。
睡眠時間無呼吸で睡眠時に呼吸が止まると、酸素不足になって、体が
休まらず睡眠不足の状態になるからです。
眠っているときに呼吸が停止したり、喉の空気の流れが弱くなったり
する病気です。
寝ているあいだに、10秒間以上の無呼吸(呼吸が止まること)もしくは
低呼吸(呼吸による換気が50%以下に低下すること)が1時間に5回以上
ある場合に睡眠時間無呼吸症候群と診断されます。
潜在患者は、人口の1~2%と言われますが、ほとんどの場合に自覚がなく、
居眠り運転で事故を起こし発見されるケースが多くあります。
最近、この病気で患者が事故を起こしたニュースがクローズアップされて
いました。
最近の研究によると、その酸素不足が原因で高血圧や糖尿病まで引き起こす
ことが明らかになってきたのです。
睡眠中に止まった呼吸が再開されるときに、酸素の量は急増します。
すると血中に「活性酸素」が発生し血管を傷つけます。
また、酸素量の急増を繰り返すと、夜に血圧を下げてくれる機能が働かなく
なり、その結果、高血圧をまねいてしまうのです。
さらに、インスリンの働きを弱めることから、糖尿病につながることまで
指摘されています。
つまり、睡眠不足になることだけが問題なのではなく、むしろ呼吸が戻る
際の急激な酸素量の回復を、一晩中何度も繰り返すことが危険だったのです。
① 無呼吸発作
「スースー」「グーグー」といったいびきではなく、数秒間、寝息が止まった
あとに「グファ!」と大きな音を発する「無呼吸発作」が特徴的です。
いびきは、空気の通り道である気道が狭くなっているサインでもあります。
「無呼吸発作」が起こるほどではなくても、習慣的ないびきがある場合には
注意が必要でしょう。
② 日中起こる過度の眠気
無呼吸発作が夜中に何十回、何百回と起こることで睡眠の質が低下し、身体と
脳が十分に休息できなくなりかねます。
その結果、日中に過度の眠気が起こり、日常生活に大きな悪影響を及ぼしていき
ます。
③女性も、やせている人も注意が必要!
睡眠時間無呼吸は、「太った男性」が患者の典型だと思われがちですが、
「やせた女性」も危険であることがわかりました。
50歳を境に、女性の患者が急増しているとのことです。
原因のひとつは、女性ホルモン「プロゲステロン」の減少によるものと考えられています。このホルモンは、脳による呼吸中枢を刺激する役割を持っています。閉経後にプロゲステロンが減少すると、呼吸を安定させる働きが弱まり、睡眠時無呼吸をまねきやすくなるのです。海外の研究では、50歳以上では患者の男女はほぼ変わらないとされています。
また、約9000人の患者を対象にした日本の大規模調査では、患者の43%が肥満ではない人でした。じつに睡眠時無呼吸の原因は「小さなあご」。太った人は舌の根元に脂肪がつくなどして気道がふさがれ、空気が通らなくなってしまいますが、もともとあごが小さい人は、口の中の容積が小さいため、舌が奥へ押しやられてしまいます。すると、ほんの少し太っただけで簡単に気道がふさがれてしまうのです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因
多くの場合、舌や口蓋垂(のどちんこ)が空気の通り道である気道をふさいで
しまうことで起こりますが、その原因はいくつかあります。
① 肥満
首のまわりに余分な脂肪がついているため、気道がふさがりやすくなってしま
います。
② 顎が小さい・狭い
気道がもともと狭いため、ふさがりやすくなってしまいます。
また、肥満でなくても体重が少し増加しただけでも睡眠時無呼吸症候群になる
リスクが高まります。
じつに睡眠時無呼吸の原因は「小さな顎」。太った人は舌の根元に脂肪がつく
などして気道がふさがれ、空気が通らなくなってしまいますが、もともとあごが
小さい人は、口の中の容積が小さいため、舌が奥へ押しやられてしまいます。
すると、ほんの少し太っただけで簡単に気道がふさがれてしまうのです。
③女性も注意が必要!
睡眠時間無呼吸は、「太った男性」が患者の典型だと思われがちですが、
「やせた女性」も危険であることがわかりました。
50歳を境に、女性の患者が急増しているとのことです。
原因のひとつは、女性ホルモン「プロゲステロン」の減少によるものと
考えられています。
このホルモンは、脳による呼吸中枢を刺激する役割を持っています。
閉経後にプロゲステロンが減少すると、呼吸を安定させる働きが弱まり、
睡眠時無呼吸をまねきやすくなるのです。
ある海外の研究では、50歳以上では患者の男女はほぼ変わらないとされて
います。
睡眠時間無呼吸症候群(SAS)の危険性
睡眠時無呼吸症候群は寝ている本人が自分で気づくのが難しい病気です。
一緒に寝ている家族などがいなければ長期間気づかず、適切な治療を受けず
に過ごしてしまうケースが多いのです。
ただ呼吸が止まるだけ、と思われがちですが、無呼吸による弊害は呼吸・
循環系を中心として身体全体に悪影響を及ぼします。
<無呼吸による呼吸・循環系の弊害>
・睡眠時呼吸性洞性不整脈(無呼吸中に頻脈と徐脈を繰り返す不整脈)
・低酸素血症(動脈血液中の酸素濃度が低くなる酸欠状態)
・呼吸性アシドーシス(肺が適切に二酸化炭素を排出しなくなる状態)
・交感神経活動の亢進(血管が収縮し、心拍数が増加・血圧が上昇すること)
睡眠時間無呼吸症候群では、寝ている間に繰り返し呼吸が止まることで、脳が
起きた状態になります。
その結果、自律神経が乱れ、内分泌に影響を及ぼし、肥満をともなって動脈硬化
や糖尿病、高血圧などの引き金になります。
さらに、繰り返される無呼吸は心臓にとって大きな負担になります。
不整脈や心疾患など、命に関わる疾患とも関連するため、早期の治療が大切です。
最近では、さまざまな疾患の背後に睡眠時無呼吸症候群が併発しやすいことが、
多くの診療科で見つかってきました。
◎睡眠時間無呼吸は自宅で診断&治療できる!
外見から睡眠時間無呼吸の危険を見抜く方法をご紹介いたします。
ひとつは、舌を出して「口蓋垂(こうがいすい):いわゆる「のどちんこ」)
が見えるかどうかで判断する方法です。
頭をまっすぐにして、口を大きく開けて舌を下に出し(このとき、声を出さない)、
口蓋垂(こうがいすい)が見えないときは睡眠時無呼吸の疑いがあります。
二つ目はあごの下と首の角度で判断する方法です。
角度が浅いと、睡眠時無呼吸の疑いがあると考えらてます。
さらに
①高血圧(とくに起床食後)
②日中の眼気や疲労
③普通の話し声よりも大きないびき
④家族や友人に無呼吸を指摘されるなど、
睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状のうちふたつ以上該当する人は、睡眠の専門医
の診察を受けることをおススメします。
睡眠時無呼吸の治療方法は、マウスピースや気道を広げると、よく眠れるだけでなく、
食欲増進ホルモンの分泌が減少するため、高血圧や肥満の改善にもつながることに
なります。
まとめ
眠時間無呼吸症候群とは、眠りが浅くなり、日中の居眠り運動などの
原因になるとされています。
睡眠時間無呼吸で睡眠時に呼吸が止まると、酸素不足になって、体が
休まらず睡眠不足の状態になるからです。
眠っているときに呼吸が停止したり、喉の空気の流れが弱くなったり
する病気です。
その原因は、①肥満であること、②顎が小さい・狭い こと、③中年の女性
の方が、なりやすいのです。
肥満の方は、首のまわりに余分な脂肪がついているため、気道がふさがり
やすく、②顎が小さい・狭い方は、気道がもともと狭いため、ふさがりやす
くなってしまいます。
また、③中年の女性の方は、女性ホルモン「プロゲステロン」の減少による
ものと考えられています。
閉経後にプロゲステロンが減少すると、呼吸を安定させる働きが弱まり、
睡眠時間無呼吸をまねきやすくなるのです。
以上のように、睡眠時間無呼吸は呼吸がとまるため恐ろしい病気であります。
しっかり、家族が支えていくことを願います。
コメント
Hello I am so glad I found your weblog, I really found you by
accident, while I was searching on Google for something else, Regardless I am here now and
would just like to say kudos for a remarkable post and
a all round interesting blog (I also love the
theme/design), I don?t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome b. http://www.01news.fr/cat%C3%A9gories/a-savoir/